10月22日、経営学部 / 経営情報学部・千島ゼミでは、くら寿司株式会社 購買本部マネージャー・大濱様、広報・IR本部ジュニアマネージャー・小山様をお招きし、「サステナブルな食の未来とイノベーション」をテーマに特別講義を開催しました。
講義ではまず、“おいしいのに市場流通が少ない低利用魚”の活用を通じて、水産資源の有効利用に挑む同社の姿勢が紹介されました。くら寿司は、魚の部位を余すことなく使う徹底した加工技術と商品開発力を強みに、「自然と資源を守りながら、新たな価値を創造する」という方針のもとで、食の持続可能性を高める取り組みを進めています。
さらに、「出店地での地域調達」と「水産揚げ地での直接調達」を使い分けることで、輸送コストの削減と鮮度維持を両立。地域経済への貢献とサプライチェーン効率化の両立を実践しています。また、商品ラインナップの拡充により、多様なニーズに応えながらも、魚の可食部分を最大限に活かし、規模の経済(Economies of Scale)を追求する経営姿勢が印象的に語られました。
講義ではまず、“おいしいのに市場流通が少ない低利用魚”の活用を通じて、水産資源の有効利用に挑む同社の姿勢が紹介されました。くら寿司は、魚の部位を余すことなく使う徹底した加工技術と商品開発力を強みに、「自然と資源を守りながら、新たな価値を創造する」という方針のもとで、食の持続可能性を高める取り組みを進めています。
さらに、「出店地での地域調達」と「水産揚げ地での直接調達」を使い分けることで、輸送コストの削減と鮮度維持を両立。地域経済への貢献とサプライチェーン効率化の両立を実践しています。また、商品ラインナップの拡充により、多様なニーズに応えながらも、魚の可食部分を最大限に活かし、規模の経済(Economies of Scale)を追求する経営姿勢が印象的に語られました。
-

特別講義をいただいた、広報・IR本部 小山様(左) / 購買本部 大濱様(右)
-

-
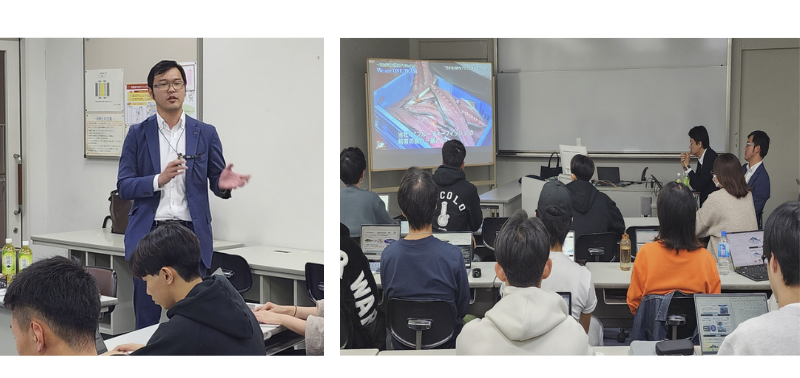
経営面で印象的だった点は、生産から販売までの一気通貫体制を確立し工程スピードを必要以上に落とさない活動でした。さらに、AIやICTを活用し過剰な属人業務化を避けながら、労働環境改善とオペレーションの効率化を図っていることがわかりました。
私たちはゼミ時間の中で、「競争戦略と社会的価値創出の両立」に取り組む企業について学ぶ機会となり、それはまさに、現代社会で必要とされるサステナビリティとイノベーションの生きた事例だったと実感することができました。
私たちはゼミ時間の中で、「競争戦略と社会的価値創出の両立」に取り組む企業について学ぶ機会となり、それはまさに、現代社会で必要とされるサステナビリティとイノベーションの生きた事例だったと実感することができました。
講義に参加した学生から出た質問として、以下のような内容が出ています。
・ エコシステムの発想で、たとえば、ドン・キホーテの海外店舗で「くら寿司の商品」を提供できれば、双方にとってWin-Win関係につながる可能性を感じました。仮にそういう方法を考えたり検討するときに、どのような情報やデータを見ますか?
・サプライチェーンでセントラルキッチンの立地を検討する条件は何ですか?
・魚の仕入れが安定しないと、店舗で商品を供給・提供する企業においては、販売機会を逃してしまうリスクに直面すると思います。実際に、調達手段のみでそうならないことは可能でしょうか?
・飲食業界では、3Dフードプリンターの活用が進んでいると聞いています。くら寿司として、 SDGsの観点から3Dプリンタを活用した食品開発に大きな可能性を感じていますか?
・同規模のチェーン店としてよく知られているスシローやはま寿司と協調したり、業界として協力すると、それが結果的に同社の成長につながるという戦略は必要でしょうか?
・サプライチェーンでセントラルキッチンの立地を検討する条件は何ですか?
・魚の仕入れが安定しないと、店舗で商品を供給・提供する企業においては、販売機会を逃してしまうリスクに直面すると思います。実際に、調達手段のみでそうならないことは可能でしょうか?
・飲食業界では、3Dフードプリンターの活用が進んでいると聞いています。くら寿司として、 SDGsの観点から3Dプリンタを活用した食品開発に大きな可能性を感じていますか?
・同規模のチェーン店としてよく知られているスシローやはま寿司と協調したり、業界として協力すると、それが結果的に同社の成長につながるという戦略は必要でしょうか?
本学では今後も、産学連携を通じて学生がリアルな経営現場を体験し、社会に貢献できる
人材の育成に務めてまいります。






