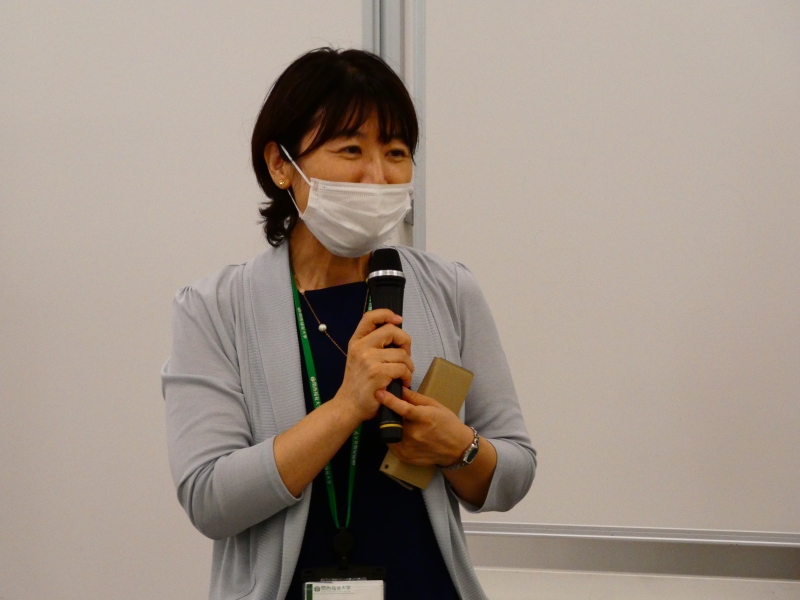9月11日(木)に、阪南大学あべのハルカスキャンパスにて、阪南大学・ハルカス大学公開講座「心のアルバムをひらく情報技術 ~回想法と情報技術による認知機能維持向上法~」を開催しました。少子高齢化が進む社会において、健康寿命の延伸と認知機能の維持は喫緊の課題で、本講座は、懐かしさを思い出す回想法と情報技術を組み合わせ、日常的な認知機能のチェックや維持、向上につながる取組みを紹介するものです。当日は参加者が40名を超え、熱気ある雰囲気の中で行われました。
講師は、本学の総合情報学部の松田健教授が務め、冒頭ではかんたん物忘れチェックから始まり、認知症やもの忘れの基礎理解から、認知症にならないための睡眠、食事、運動や人とのつながり、脳トレの重要性について解説されました。特に、予防、対策に関わる生活習慣として、「よく食べ、よく遊び、よく寝る」のゴールデンルールを強調されていました。日常の積み重ねが脳の健康を支えるというメッセージが、参加者の共感を呼びました。
メインプログラムでは、情報技術を活用した体験型の脳トレとして「思い出画像復元ゲーム」と「ことばを当てるゲーム」を実施されました。参加者はスマートフォンなど用いて、昔の写真を使いパズルゲームで懐かしい記憶を呼び起こし、それを周りの人に話しながら交流を深めていきました。各テーブルには関西福祉大学の看護学部の学生がサポートし、思い出画像復元ゲームの補助だけでなく、世代を超えた交流も自然に生まれました。「脳を使って心を動かす」活動を日常に取り入れることの大切さを、参加者とスタッフがともに実感する時間となりました。
会場では、ゲーム体験前後の回想法を通じて、「昔のことを思い出し、誰かに話したくなったか」「交流を深められたか」「日常的に継続したいか」「気持ちが明るく、楽しくなったか」といった観点から、に簡単なアンケートを実施されました。
最後の質疑応答では、親の認知症に関する質問があり、公開講座をサポートして頂いている専門分野を担当する関西福祉大学の前川教授が、認知症の特徴や具体的な対応策について助言を行いました。今回の公開講座では、情報技術を組み合わせることで、楽しみながら日常的に認知機能の維持・チェックにつなげていける可能性を示しました。
この度の公開講座実施に際しては、本学企業情報研究科の2名の学生のほか、関西福祉大学の前川教授とゼミ学生9名に運営のサポートをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
※本学は引き続き、講座やイベントの実施を通して学生支援、地域貢献、生涯学習、社会人教育等、あべのハルカスの企業・施設とつながることができる様々な連携事業を行ってまいります。
講師は、本学の総合情報学部の松田健教授が務め、冒頭ではかんたん物忘れチェックから始まり、認知症やもの忘れの基礎理解から、認知症にならないための睡眠、食事、運動や人とのつながり、脳トレの重要性について解説されました。特に、予防、対策に関わる生活習慣として、「よく食べ、よく遊び、よく寝る」のゴールデンルールを強調されていました。日常の積み重ねが脳の健康を支えるというメッセージが、参加者の共感を呼びました。
メインプログラムでは、情報技術を活用した体験型の脳トレとして「思い出画像復元ゲーム」と「ことばを当てるゲーム」を実施されました。参加者はスマートフォンなど用いて、昔の写真を使いパズルゲームで懐かしい記憶を呼び起こし、それを周りの人に話しながら交流を深めていきました。各テーブルには関西福祉大学の看護学部の学生がサポートし、思い出画像復元ゲームの補助だけでなく、世代を超えた交流も自然に生まれました。「脳を使って心を動かす」活動を日常に取り入れることの大切さを、参加者とスタッフがともに実感する時間となりました。
会場では、ゲーム体験前後の回想法を通じて、「昔のことを思い出し、誰かに話したくなったか」「交流を深められたか」「日常的に継続したいか」「気持ちが明るく、楽しくなったか」といった観点から、に簡単なアンケートを実施されました。
最後の質疑応答では、親の認知症に関する質問があり、公開講座をサポートして頂いている専門分野を担当する関西福祉大学の前川教授が、認知症の特徴や具体的な対応策について助言を行いました。今回の公開講座では、情報技術を組み合わせることで、楽しみながら日常的に認知機能の維持・チェックにつなげていける可能性を示しました。
この度の公開講座実施に際しては、本学企業情報研究科の2名の学生のほか、関西福祉大学の前川教授とゼミ学生9名に運営のサポートをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
※本学は引き続き、講座やイベントの実施を通して学生支援、地域貢献、生涯学習、社会人教育等、あべのハルカスの企業・施設とつながることができる様々な連携事業を行ってまいります。