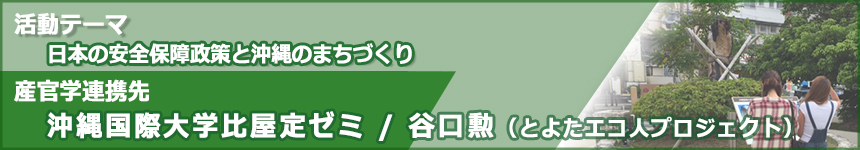活動の目的及び取り組む課題
日本の安全保障政策のなかに組み込まれた沖縄は、米軍基地との関係で国際法上も他の地域とは異なる地位に置かれ、その「まちづくり」も政府主導の「沖縄の本土化」路線による沖縄優遇政策が展開されてきた。一方的に負担と優遇を押しつけられる沖縄の側からは、それに対する抵抗と従属が繰り返され、政治学的、経済学的、社会学的に一貫した将来のまちづくりに関する展望が見いだせない。このゼミでは、日本の安全保障政策に組み込まれた沖縄の歴史と現状について総括し、政府主導の沖縄のまちづくりのあり方を再検討し、その上で、沖縄のあるべきまちづくりと開発について検討することを目的とする。
また、キャリアゼミとしては、地域開発やまちづくりについての基礎的知識を身につけ、NPO法人と連携することで社会のなかでNPOのような公的機関や営利企業とも異なる第三の存在が果たす役割やその仕事について学ぶことも目的としている。
また、キャリアゼミとしては、地域開発やまちづくりについての基礎的知識を身につけ、NPO法人と連携することで社会のなかでNPOのような公的機関や営利企業とも異なる第三の存在が果たす役割やその仕事について学ぶことも目的としている。
活動内容
このゼミでは、国家レベルの政府による安全保障政策や開発政策という政治学的視点、国内の地域開発についての経済学的視点、地域的コミュニティ形成や「まちづくり」についての社会学的視点の3つの視点から、沖縄のまちづくりについて検討することを目的として研究を行った。
予備研究から、本土とは異なる利点と制約をもつ沖縄の産業について、農業と観光を中心に産業分野をしぼり、開発の方向性を見いだした。その際、現地である沖縄の若者の声を反映させるべく、沖縄国際大学の比屋定ゼミと共同研究を行った。さらに、地域的コミュニティ形成やまちづくりについて地方公共団体と協同活動しているNPO法人である「とよたエコ人プロジェクト」の役員であり、沖縄のまちづくりについて長く調査研究をしている谷口功氏の指導の下、現地調査の結果から提案すべきまちづくりの方向性を示し、評価していただいた。
予備研究から、本土とは異なる利点と制約をもつ沖縄の産業について、農業と観光を中心に産業分野をしぼり、開発の方向性を見いだした。その際、現地である沖縄の若者の声を反映させるべく、沖縄国際大学の比屋定ゼミと共同研究を行った。さらに、地域的コミュニティ形成やまちづくりについて地方公共団体と協同活動しているNPO法人である「とよたエコ人プロジェクト」の役員であり、沖縄のまちづくりについて長く調査研究をしている谷口功氏の指導の下、現地調査の結果から提案すべきまちづくりの方向性を示し、評価していただいた。
代表学生の感想

米軍基地に加えて、本州の巨大消費地からの地理的な「距離」という制約をもつ沖縄の農業は、長くサトウキビとパイナップルを主要な作物として生産してきた。しかし、本土復帰後、儲けの少ない農業から観光産業へと基幹産業が変遷し、沖縄農業は衰退の一途をたどってきた。そのような沖縄農業の将来の可能性について、高付加価値の作物の生産を始めた一部の農家とそれへの支援という点から検討した。
新しい高付加価値作物の生産に挑戦されているJAおきなわ北中城支店果樹専門部会会長の比嘉善春さんの農園を訪れ、インタビューさせていただいた。比嘉さんが生産されているのは本州でも人気があり、沖縄の風土に適したマンゴーである。比嘉さんは、マンゴーの付加価値を高めるため、ハウスの建設、枝や葉を横に伸ばす育成法、土に混ぜる酵素やEM菌など、さまざまな方法を考案され実施されていた。
そのような新しい沖縄農業には大きな可能性があると考えるが、そのためには、莫大になる初期投資や、本州への輸送などの面で国や県が積極的な支援を行える体制を作っていく必要があると考えた。
新しい高付加価値作物の生産に挑戦されているJAおきなわ北中城支店果樹専門部会会長の比嘉善春さんの農園を訪れ、インタビューさせていただいた。比嘉さんが生産されているのは本州でも人気があり、沖縄の風土に適したマンゴーである。比嘉さんは、マンゴーの付加価値を高めるため、ハウスの建設、枝や葉を横に伸ばす育成法、土に混ぜる酵素やEM菌など、さまざまな方法を考案され実施されていた。
そのような新しい沖縄農業には大きな可能性があると考えるが、そのためには、莫大になる初期投資や、本州への輸送などの面で国や県が積極的な支援を行える体制を作っていく必要があると考えた。
国際コミュニケーション学部 3年生 平野 真由
参加学生一覧

加藤 優奈、萩原 美麗、氷海 世奈、平野 真由、福角 太智、堀之内 つばさ、山森 美咲
連携団体担当者からのコメント
とよたエコ人プロジェクト 谷口 功 氏
沖縄について、現状の表面的な情報だけでなく、古い歴史や風土、文化まで含めた幅広い事前研究を行い、さまざまな沖縄のまちづくりの可能性について検討し、現地でインタビューや調査を行い、農業や観光について沖縄の将来のまちづくりの方向性を示しています。企業や公的機関でもない、もうひとつのNPOのような視点があり、マーケットや政治からはこぼれ落ちてしまう社会の一側面があることを知っていただけたのはよかったと思います。
教員のコメント
国際コミュニケーション学部 井上 裕司 教授
大学での事前の研究から、沖縄が本州の大阪などとは異なる利点と制約を持つことを学び、そのなかでどうやって今後、政府や企業や市民がまちづくりをしていくべきなのかを考察することがこのゼミの目的です。視点は、国や県などの政治や、企業などのビジネスとも異なる、より市民の側に立ったNPOの立場に置きました。沖縄で、沖縄の市民が、その風土や文化などの特色を生かし、また、本州からの距離や米軍基地などのさまざまな制約をできるかぎり最小限に抑えつつ、いかに幸せに暮らしてのかについて学生達には考えてもらいました。それは、単なる営利目的の商品開発や観光開発のレベルを超えて、政治・経済・社会の多様な側面から市民の生活を考える視点です。学生達は、さまざまな産業があるなかで、農業と観光に沖縄の将来の可能性を見いだし、それを沖縄の良さを生かしつつ、いかに政策やまちづくりを通じて伸ばしていけるかを考えました。このような経験が、単なる一企業ではなく、広く社会を見る視点を伸ばし、将来のキャリア形成に生かされればよいと考えます。