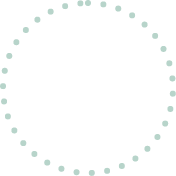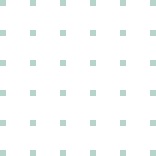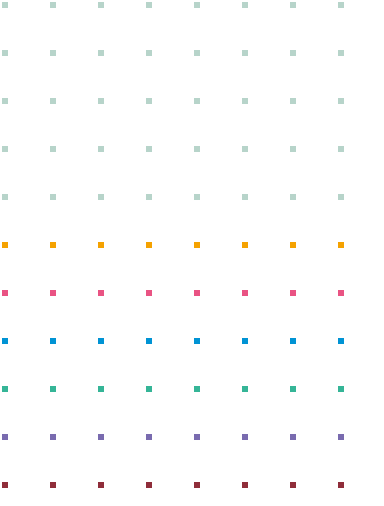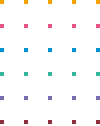ライバル関係と新たなビジネス・パラダイム「協争」
メガ・コンペティション時代と言われている現代社会を生きる多くの人々は、中身はどうであれ、「スローライフ」という言葉に惹かれるほど、コンペティション(競争)状況に疲れやストレスを感じています。行き過ぎた競争意識でお互いに破滅的な状況に陥るケースも少なくないので、当然のことだとは考えられます。しかし、多くの場合、競争関係の形成はプラス効果があり、特に企業の成長の原動力として作用してきたことは否定できません。なにより、競争相手、つまり、ライバルからの刺激は本人の競争力を向上させる大きな力になります。個人であれ、集団であれ、そのような競争を見守る観衆の楽しみもあります。
ジャズ音楽の世界もライバルたちの競争によって発展し、市場も成熟してきました。本格的なジャズの形成期にお互いに交流しながら競争した黒人のルイ・アームストロングと白人のビックス・バイダ—ベックは、特筆すべき人たちです。彼らによってジャズ音楽の世界がより楽しくなったからです。また、1930年代にはベニー・グッドマンとチック・ウェブが自分のスウィングバンドを率いって演奏対決したあるクラブには4千人の観衆が集まったとも言われています。現在、我々がスポーツなどのライバル・マッチに熱狂することと同じです。
ジャズ音楽の世界もライバルたちの競争によって発展し、市場も成熟してきました。本格的なジャズの形成期にお互いに交流しながら競争した黒人のルイ・アームストロングと白人のビックス・バイダ—ベックは、特筆すべき人たちです。彼らによってジャズ音楽の世界がより楽しくなったからです。また、1930年代にはベニー・グッドマンとチック・ウェブが自分のスウィングバンドを率いって演奏対決したあるクラブには4千人の観衆が集まったとも言われています。現在、我々がスポーツなどのライバル・マッチに熱狂することと同じです。
ホット(Hot)なルイ・アームストロング
ルイ・アームストロングは、不明な点もありますが、1901年、ニューオーリンズで生まれたと知られています。両親の離婚により祖母の下で育った彼は、祖母と一緒に教会に通いました。教会合唱団や牧師のシャウトなど、彼の最初の音楽体験はゴスペルにあったかもしれません。小学校時代には四重唱団を作り街頭で歌い始めます。11歳の時には町のパレードでピストルを発射し、少年院に収監されることになります。当時の少年院にはブラスバンドがあり、休日にはジャズ・クラブで演奏会を行ったりしました。ルイ・アームストロングはそのブラスバンドのリーダーとして成長しました。少年院を出た彼はシカゴに行ってキング・オリバー・バンドに参加します。その後の彼の演奏スタイルは実に多くのジャズ・ミュージシャンに影響を与えました。
具体的にみると、サックス奏者コールマン・ホキンスはリズム楽器のように吹いたがルイ・アームストロングの演奏を聴いてからアドリブ楽器としてのサックス奏法を開拓するようになったと言われています。ピアノもそれまでにはピアニストが無伴奏でソロ演奏をするか、バンドにピアノの音が埋もれないように力強く楽器を鳴らすことが定番の演奏でしたが、ルイ・アームストロング以来、多くのピアニストたちは、右手でアドリブ・プレーズ、左手でコード(和音)を押すという、現在にはジャズピアノの基礎として知られている演奏スタイルを作り上げました。また、ルイ・アームストロングの演奏に魅了された編曲者(ドン・レッドマン)は、ルイ・アームストロングの持つ演奏力量を最大限引き出すために新たな類型の楽譜を考案し、ビック・バンドの新しい編曲方式を構築した人物として知られるようにもなりました。何回も言いましたが、ジャズ・ヴォーカルにスキャット・唱法を導入したこともルイ・アームストロングの功績です。彼は、コルネットの音をそのまま人間の声に写したようなスタイルで歌いました。もちろん、ルイ・アームストロング以前からジャズ音楽は存在しましたが、彼によってはじめてジャズは個人技の音楽、アドリブ(インプロヴィゼーション)の芸術としての形が作られたということです。
具体的にみると、サックス奏者コールマン・ホキンスはリズム楽器のように吹いたがルイ・アームストロングの演奏を聴いてからアドリブ楽器としてのサックス奏法を開拓するようになったと言われています。ピアノもそれまでにはピアニストが無伴奏でソロ演奏をするか、バンドにピアノの音が埋もれないように力強く楽器を鳴らすことが定番の演奏でしたが、ルイ・アームストロング以来、多くのピアニストたちは、右手でアドリブ・プレーズ、左手でコード(和音)を押すという、現在にはジャズピアノの基礎として知られている演奏スタイルを作り上げました。また、ルイ・アームストロングの演奏に魅了された編曲者(ドン・レッドマン)は、ルイ・アームストロングの持つ演奏力量を最大限引き出すために新たな類型の楽譜を考案し、ビック・バンドの新しい編曲方式を構築した人物として知られるようにもなりました。何回も言いましたが、ジャズ・ヴォーカルにスキャット・唱法を導入したこともルイ・アームストロングの功績です。彼は、コルネットの音をそのまま人間の声に写したようなスタイルで歌いました。もちろん、ルイ・アームストロング以前からジャズ音楽は存在しましたが、彼によってはじめてジャズは個人技の音楽、アドリブ(インプロヴィゼーション)の芸術としての形が作られたということです。
クール(Cool)なビックス・バイダ—ベック
ビックス・バイダ—ベック(1903〜1981)は、ドイツ移民の子孫としてアイオワ州で生まれました。15歳の頃からコルネットを吹き始めた彼は、ODJBのレコードを聴きながら独学でジャズを学び、18歳の頃から大衆の前で演奏をはじめます。ルイ・アームストロングがニューオーリンズからシカゴに移住してキング・オリバー・バンドで人気を集めるようになった1923年に、ビックス・バイダーベックは、ウルヴァリンズという、後に最初のシカゴスタイルのジャズ・バンドとして評価されたバンドで演奏をしていました。ビックス・バイダ—ベックの演奏の特徴としては、後日マイルス・デイヴィスに繋がるノン・ヴィブラート奏法、黒人の過度な感情噴出を排除した簡潔で軽快な多声音楽形式の即興、ヨーロッパの近代音楽を反映したハーモニック・センスなどが言われています。
ビックス・バイダーベックの全盛期は、ルイ・アームストロング・スタイルが流行った時期であったことを考えると、彼の奏法が如何に独創的で新鮮だったかは言うまでもありません。ビックス・バイダ—ベックの即興的なプレーズにはピアノを弾いた母親の影響で吸収したヨーロッパ音楽の影があるという論者もいます。ヴィブラートを使用しない独特な演奏法はヨーロッパのトランペット奏者たちには普通で、感情過剰の反対側にある明晰さ、洗練さなどのキーワードがヨーロッパ文化の伝統であるということです。
28歳の若さで亡くなってしまい、伝説的な存在になった彼にはある種の評価が付きものでした。ジャズ音楽の暗い側面、つまり、憂鬱で、孤独で、感傷的な、まるで捨てられた人の悲しみみたいなものが感じられるということです。彼は、華麗だが憂鬱、退廃的で浪漫的な時代だと言われたシカゴスタイルの証人としても評価されました。ドイツのジャズ評論家のべレントは、ビックス・バイダ—ベックによってドイツの浪漫主義とそれに潜められた全ての情緒がジャズに導入されたとまで指摘しています。
つまり、ルイ・アームストロングにアフリカの音楽的遺産があるとすれば、ビックス・バイダ—ベックにはドイツの浪漫主義があったということです。このような見方から、それまでに黒人のコピーにとどまっていた白人たちのジャズ演奏がビックス・バイダ—ベックの登場により初めてルーツのあるオリジナリティを獲得したと評価する人もいます。黒人の真似ではなく白人なりのジャズが可能だということを彼が示してくれたということです。
ビックス・バイダーベックの全盛期は、ルイ・アームストロング・スタイルが流行った時期であったことを考えると、彼の奏法が如何に独創的で新鮮だったかは言うまでもありません。ビックス・バイダ—ベックの即興的なプレーズにはピアノを弾いた母親の影響で吸収したヨーロッパ音楽の影があるという論者もいます。ヴィブラートを使用しない独特な演奏法はヨーロッパのトランペット奏者たちには普通で、感情過剰の反対側にある明晰さ、洗練さなどのキーワードがヨーロッパ文化の伝統であるということです。
28歳の若さで亡くなってしまい、伝説的な存在になった彼にはある種の評価が付きものでした。ジャズ音楽の暗い側面、つまり、憂鬱で、孤独で、感傷的な、まるで捨てられた人の悲しみみたいなものが感じられるということです。彼は、華麗だが憂鬱、退廃的で浪漫的な時代だと言われたシカゴスタイルの証人としても評価されました。ドイツのジャズ評論家のべレントは、ビックス・バイダ—ベックによってドイツの浪漫主義とそれに潜められた全ての情緒がジャズに導入されたとまで指摘しています。
つまり、ルイ・アームストロングにアフリカの音楽的遺産があるとすれば、ビックス・バイダ—ベックにはドイツの浪漫主義があったということです。このような見方から、それまでに黒人のコピーにとどまっていた白人たちのジャズ演奏がビックス・バイダ—ベックの登場により初めてルーツのあるオリジナリティを獲得したと評価する人もいます。黒人の真似ではなく白人なりのジャズが可能だということを彼が示してくれたということです。
ライバルの競争とジャズの調和
トビアス(2003)は、ストーリーを構成する面白いプロットの1つにライバルの存在を挙げています。二人が同じ目的を持って闘うときにライバル関係が形成されますが、ストーリーにライバルを登場させるには一定の規則があると言います。それは、敵対する2つの勢力が同じ力を持つことで、物理的な勢力の大きさではなく、筋肉質の巨人に比べて身体的に弱い人は知能で闘えるという意味です。いずれにせよ、二人が同時に勝利することはあり得ず、「一人は勝ち、一人は負け」というのがトビアスのライバル観ですが、ジャズの世界においては状況が違います。韓国ジャズの第1世代の一人として称えられているキム・ジュンは次のように語ったことがあります。
「ジャズの世界には張り合いがない。他のジャンルは演奏者同士で競争意識があるが、ジャズ・ミュージシャンたちはお互いを認め合うのが良い。ジャズ・ミュージシャンが一番望んでいるのは、レベルの似た演奏者同士で共に呼吸を合わせることであり、そのようにするためには絶え間なく練習するしかない」(ドンア日報、2011.1.21)
もちろん、すべてのジャズ・ミュージシャンがそうであるとは限らないでしょう。個人と集団の調和を具現するジャズ音楽をやっている人たちなので、ライバルに対しても少し違う見方をしているのかもしれません。実際に、ルイ・アームストロングもビックス・バイダ—ベックの音楽が好きで、彼の演奏をよく聴きに行ったと知られています。
「ジャズの世界には張り合いがない。他のジャンルは演奏者同士で競争意識があるが、ジャズ・ミュージシャンたちはお互いを認め合うのが良い。ジャズ・ミュージシャンが一番望んでいるのは、レベルの似た演奏者同士で共に呼吸を合わせることであり、そのようにするためには絶え間なく練習するしかない」(ドンア日報、2011.1.21)
もちろん、すべてのジャズ・ミュージシャンがそうであるとは限らないでしょう。個人と集団の調和を具現するジャズ音楽をやっている人たちなので、ライバルに対しても少し違う見方をしているのかもしれません。実際に、ルイ・アームストロングもビックス・バイダ—ベックの音楽が好きで、彼の演奏をよく聴きに行ったと知られています。
ライバル観の再検討
筆者の好きな日本漫画に手塚治虫の『ブラック・ジャック』シリーズがあります。ある日、書店で「心の傷を治す99の言葉」という副題で『ブラック・ジャック語録』を見つけて一瞬で読みましたが、そこにもライバルに関する話がありました。天才的な外科医であるが無免許医師として闇の世界で稼いているブラック・ジャックですが、彼のライバルは、ドクター・キリコなどの悪徳医師たちではなく、自分並みの腕を持っている他の医師だということです。
-

『ブラック・ジャック』第238話「過ぎ去りし一瞬」
語録編集者によると、ドクター・キリコなどは、職業は同じだが、目指すものや、やり方で大きな違いがあるから真のライバルとは言えません。ブラック・ジャックは自分の腕で患者を直すことが目的であり、お金が目的ではないからです。独りぼっちの自分にも仲間がいるという嬉しさもあり、お互いに尊重しながら正当なやり方で競い合うことの大事さを言っているわけです。お互いの心の支えになる刺激的な関係であるということです。
敵対的な関係でお互いに破滅的な競争を繰り広げているライバルも、善意の競争関係を通じて共に成長しているライバルも、それを見守っている観衆の立場は楽しいことです。ただ一つ指摘しておきたいのは、小説のなかのライバルは、片手が破滅しないと面白くないかもしれませんが、ビジネス世界ではそうではないということです。合法的で正当なやり方での競争が求められているビジネス世界では、ジャズ・ミュージシャンのようなプラスのライバル関係がより重要であると考えられます。ルイ・アームストロングとビックス・バイダ—ベックがそれぞれ優れたトランペット奏者としてお互いを意識しながらホットとクールという創造的な独自の領域が構築され、ジャズファンが増え続けたことと同じく、個人、組織、企業間においても「Win-Win」の競争関係の形成が重要なのではないでしょうか。
敵対的な関係でお互いに破滅的な競争を繰り広げているライバルも、善意の競争関係を通じて共に成長しているライバルも、それを見守っている観衆の立場は楽しいことです。ただ一つ指摘しておきたいのは、小説のなかのライバルは、片手が破滅しないと面白くないかもしれませんが、ビジネス世界ではそうではないということです。合法的で正当なやり方での競争が求められているビジネス世界では、ジャズ・ミュージシャンのようなプラスのライバル関係がより重要であると考えられます。ルイ・アームストロングとビックス・バイダ—ベックがそれぞれ優れたトランペット奏者としてお互いを意識しながらホットとクールという創造的な独自の領域が構築され、ジャズファンが増え続けたことと同じく、個人、組織、企業間においても「Win-Win」の競争関係の形成が重要なのではないでしょうか。
新たなビジネス・パラダイム、「協争」
近年の企業間競争は新しい局面に向かっているようです。競争するだけではなく、協力すべきことは協力するという動きです。マーケティング戦線では血まみれの戦いになるかもしれませんが、物流やお互いに競争力のない分野では協力するということです。過去にも類似した事例がなかったわけではないので、新しいパラダイム云々は言い過ぎかもしれませんが、特に21世紀に入ってから頻繁に見かけるようになったのも事実です。
実際に、2017年1月3日の日本経済新聞には、「協争」の時代が来たというタイトルの記事もありました。競争相手であるハウス、カゴメ、味の素の3社が2014年から配送部門で手を組むようになったことや、2008年からヤマハ発動機とホンダが小型スクーター開発と生産に協力するようになったことなどの事例をベースに昨日の敵は今日の友という副題を出しています。
勿論、このようなライバル同士の協力関係は、日本国内で日本企業同士の間だけの話ではありません。もう十数年前のことですが、テレビ市場で激しい戦いを繰り広げていたソニーとサムスン電子が手を組んで、LCDパネル製造専門の会社まで作って、世界のプラット・テレビ市場でLCDテレビの優位を確固たるものにしたのは有名な話です。もはや、グローバルの時点で日常的に企業間の合従連衡が行われているのが現実でしょう。このような現象は、ジャズ・ミュージシャンが、実力さえあれば、誰とでもインプロヴィゼーションができるという話と同じであるような気がします。
実際に、2017年1月3日の日本経済新聞には、「協争」の時代が来たというタイトルの記事もありました。競争相手であるハウス、カゴメ、味の素の3社が2014年から配送部門で手を組むようになったことや、2008年からヤマハ発動機とホンダが小型スクーター開発と生産に協力するようになったことなどの事例をベースに昨日の敵は今日の友という副題を出しています。
勿論、このようなライバル同士の協力関係は、日本国内で日本企業同士の間だけの話ではありません。もう十数年前のことですが、テレビ市場で激しい戦いを繰り広げていたソニーとサムスン電子が手を組んで、LCDパネル製造専門の会社まで作って、世界のプラット・テレビ市場でLCDテレビの優位を確固たるものにしたのは有名な話です。もはや、グローバルの時点で日常的に企業間の合従連衡が行われているのが現実でしょう。このような現象は、ジャズ・ミュージシャンが、実力さえあれば、誰とでもインプロヴィゼーションができるという話と同じであるような気がします。